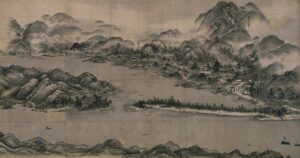アートリエ編集部が、絵画を活用した節税についてわかりやすく解説します。
絵画は事業用であれば経費にできるため、節税に役立てられる可能性がありますが、金額によっては経費処理が難しいこともあります。
「本当に経費になるの?」と思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、絵画を経費として計上する方法や、個人事業主・法人が経費にする際のルール、注意点を紹介します。
絵画と節税の関係を理解し、経費処理を検討する際の参考にしてみてください。
※本記事の内容は、一般的な情報をもとに作成したものであり、税理士など専門家による監修は行っておりません。具体的な会計・税務の判断については、必ず専門家へご確認ください。
絵画が節税になるのはなぜ?

絵画が節税につながるとされる理由は、適切な扱いを行えば、購入した絵画が減価償却の対象となるケースがあるためです。
2015年の税制改正により、100万円未満の絵画を含む美術品は原則として「減価償却資産」の対象になりました。
しかし、対象となるのは、絵画が「時の経過とともにその価値が減少するもの」と認められた場合です。
購入額や条件によっては対象とならないケースもありますが、個人事業主や法人が絵画を購入することで、節税できる可能性があります。
絵画の節税に関係する減価償却資産の概要

減価償却資産は、事業用途に用いられ、時間の経過や使用する過程で価値が減少する資産が対象とされます。減価償却とは、資産の取得費用を一度に経費計上せず、法定耐用年数に応じて分割し、少しずつ経費化していく仕組みのことです。
取得価額が10万円以上20万円未満の資産は「一括償却資産」として、3年間均等に費用配分できる制度が認められています。ただし、歴史的価値の高い古美術品や希少性のある作品は除外されます。
絵画で節税する条件

絵画を節税に活用するためには、主に「購入金額が100万円以下であること」と「事業目的で使用されていること」がポイントになります。
それぞれの条件を詳しく見ていきましょう。
取得価格が1点100万円未満であること
絵画を節税目的で扱う場合、1点あたりの取得価格が100万円未満であることが一般的な基準とされています。取得価額が100万円以上の場合は、原則として減価償却の対象外(非減価償却資産)となり、経費として計上できません。
ただし、時間が経過して価値が下がるものは、100万円以上でも減価償却資産に認められることがあります。
事業目的で使用される絵画であること
絵画を節税の対象とするには、事業用途で使用されていることが条件です。絵画の場合は、来訪者が目にする場所に設置されていれば、事業用と認められる傾向にあります。
ただし、用途と実態に間違いがあれば否認されることもあるため、展示場所や設置方法などを記録しておくと安心です。
減価償却ができない絵画・美術品の例

国税庁によると、「時の経過によりその価値が減少することが明らかでないもの」は、減価償却資産には該当しないとされています。
著名な画家や彫刻家による美術的価値の高い作品は、歴史的・芸術的評価が定まっており、価値が下落しにくいことから、原則として減価償却の対象には認められていません。
そのほか、古美術品・出土品といった代替性がない歴史的な価値があるものや、展示用途が明確でないものは減価償却資産の対象外とされています。
絵画で節税する際の経費計上の基準
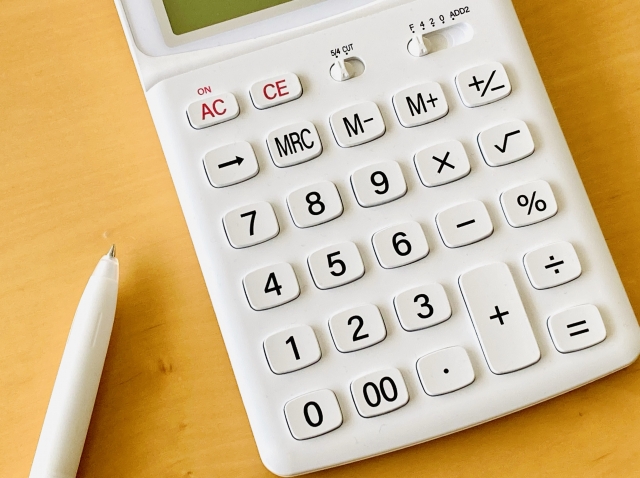
絵画を経費として計上するには、取得価額が100万円未満である場合に、減価償却資産として扱われるとされています。
また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産は、「一括償却資産」として扱われ、3年間で均等に償却できるとされています。
通常の減価償却と比べて早期に経費化できる点が特徴です。
【金額別】絵画の節税方法

ここからは、購入額別に節税する方法を解説します。
10万円未満
取得価格が10万円未満の物品については、実務上、少額資産として「消耗品費」などで経費処理されるケースが一般的です。これは税法上の「少額減価償却資産」の取扱いを参考にした考え方によるものです。
10万円~20万円未満の絵画
取得価額が10万円以上20万円未満の絵画は、「一括償却資産」として扱えます。
国税庁によると、この区分に属する資産は取得してから3年間にわたり、取得価額の3分の1ずつを経費計上できるとされています。
一括償却資産とする処理は、法定耐用年数に従う通常の減価償却と比べて経費化が早く進むため、節税に役立つ場合があります。
ただし、この制度を適用するには、事業用途であることや価値の減少性が認められることなど、一定の基本要件を満たす必要があります。
20万円~30万円未満
取得価額が20万円以上30万円未満の場合は、「少額減価償却資産の特例」を利用するか、通常の減価償却資産として扱うケースがあります。
「少額減価償却資産の特例」は、条件を満たした個人事業主や法人であれば適用できるとされています。減価償却資産として扱う場合は、法定耐用年数に応じて分割して経費化する方法が一般的です。
30万円~100万円未満
取得価額が30万円以上、100万円未満の絵画は通常の減価償却資産として扱われ、法定耐用年数に従って分割して経費化するのが一般的です。
なお、絵画の法定耐用年数は、8年とされています。
100万円以上の絵画の勘定科目
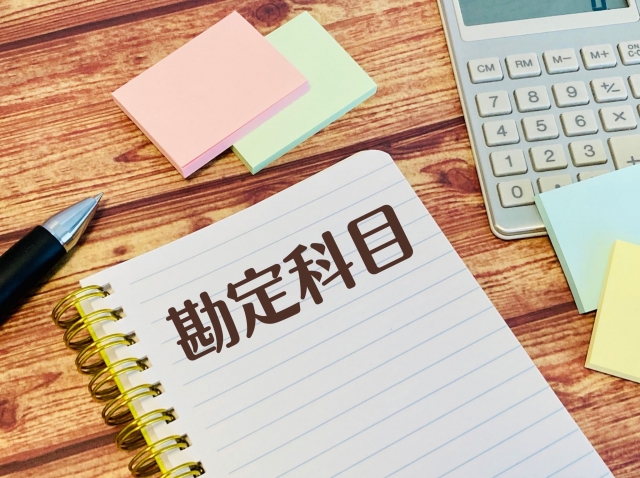
100万円以上の絵画を経費として計上する際には、慎重な判断が求められる場合があります。
ここからは、主な計上方法と例外について紹介します。
100万円以上の絵画は減価償却できない
取得価額が1点100万円以上の絵画は、原則として非減価償却資産として扱われ、減価償却の対象として認められません。
ただし、条件によっては認められるケースもあります。次の項目で、その具体的な条件を見ていきましょう。
100万円以上でも減価償却が可能な特例
100万円以上であっても、減価償却が認められることもあります。認められる条件は、以下のとおりです。
- 会館のロビーや葬祭場のホールなど、不特定多数の人が出入りする場所で装飾や展示のために設置されるものであること(※有料で公開するものは除く)
- 移動や取り外しが難しく、その場所での利用を前提としていることが明らかなものであること
- 仮にほかの目的に転用しようとしても、設置状況や使用の実態からみて美術品としての市場価値が期待できないものであること
引用元:国税庁「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」
これらの条件をすべて満たす場合は、減価償却の対象となる場合もあります。
絵画を購入して節税対策する際の注意点

絵画を活用して節税を検討する際は、次の点に注意が必要です。
- 絵画の付随費用も取得価格に含まれる
- 少額減価償却資産の特例における条件に注意
- 贈答用の絵画は減価償却資産にならない
1つずつ詳しく解説します。
絵画の付随費用も取得価格に含まれる
絵画を購入する際の取得価額には、作品の本体価格だけでなく、次のような付随費用も含まれる場合があります。
- 配送運賃
- 荷役費
- 運送保険料
- 購入手数料
- 関税(輸入時など)
- 額縁 など
このように、絵画の取得価額には本体価格以外の費用も含まれるため、合計額を正確に把握しておくことが重要とされています。
少額減価償却資産の特例における条件に注意
少額減価償却資産の特例における条件は、以下のとおりです。
- 青色申告を行っている個人事業主や中小企業であること
- 資本金が1億円以下であること
- 常時使用する従業員が1,000人以下であること
これらの条件を満たす場合には、特例を適用できる場合があります。
適用の可否や処理方法については、事前に税理士などの専門家へ確認することをおすすめします。
贈答用の絵画は減価償却資産にならない
顧客や取引先への贈呈目的で購入した絵画は、原則として減価償却資産には認められていません。
絵画を節税目的で扱う際には、作品が展示や装飾用途であり、贈答目的ではないことを明確にしておくことが重要です。
贈答品は事業用固定資産ではなく、「交際費」や「広告宣伝費」といった勘定科目で処理するのが一般的です。
法人への贈答に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。
節税以外にもある!個人事業主や法人がアートを購入するメリット

個人事業主や法人がアートを購入するメリットには、次のようなものがあります。
- 文化的な価値を蓄えられる
- ストレスを軽減できる
- ブランディングができる
ここでは、節税以外のメリットを順に紹介します。
文化的な価値を蓄えられる
絵画は希少性や画家の認知度によって市場価値が保持されやすいため、文化的な価値を持つ場合があります。
無名の画家による作品であっても、将来評価が高まれば価格が上昇する可能性もあります。
ただし、価格変動や流動性のリスクもあるため、あくまで「文化的な価値を持つものになる可能性を持つ」として捉えることが大切です。
ストレスを軽減できる
絵画をオフィスに設置することで、従業員や来訪者のストレスを軽減する効果が報告されています。
また、視覚的な刺激によって想像力が高まったり、新しい発想が生まれたりするなど、創造的な環境づくりに寄与する可能性もあります。
穏やかな色合いの風景画などを取り入れると、職場の雰囲気が和らぎ、ストレスの緩和やリラックス効果が期待できるでしょう。
ブランディングができる
アートは、企業や事業者の理念・世界観・価値観を視覚的に表現するツールとしても機能します。来訪者が目にするエントランスや受付、応接室などにアートを置くことで、第一印象を良くして企業イメージの向上につなげることができます。
また、アートを通じて企業の文化や感性を伝えることで、社員の誇りや結束力の強化などにも寄与する可能性もあります。
アートとビジネスの関連性は以下の記事でも紹介しているので、ぜひ併せてご覧ください。
絵画と節税に関するよくある質問

ここでは、よくある質問に回答します。ぜひ参考にしてみてください。
絵画を国に寄付すると節税できますか?
法人が美術品を国などの公的機関へ寄付した場合、一定の条件を満たすことで、その時価相当額を損金として所得から控除できる場合があります。
この制度は、個人や企業が保有する美術品が一般に公開されず、所在不明となることを防ぎ、美術館などで展示・保存されるよう促す目的で設けられています。
詳細な取り扱いは、寄付先や作品の評価額によって異なるため、事前に税理士や専門機関へ確認することをおすすめします。
サラリーマンでも絵画を購入して節税できますか?
サラリーマンが個人で絵画を購入しても、原則として節税目的での経費計上は認められていません。ただし、副業などで継続的に事業所得を得ており、個人事業主と認められる場合には、減価償却による経費化が可能とされています。
このような場合でも、事業としての実態が明確であることが前提です。
まとめ

この記事では、絵画を購入した際の節税方法を解説しました。
購入した絵画が、100万円以下であれば、節税対策の対象となる可能性が高い一方で、用途や設置状況、付随費用を含む取得価格で判断が分かれます。
ただし、法人や顧客などに贈答する目的で購入した場合には、経費として認められないため対象外となります。一方、事務所や店舗などの装飾用途で使用する絵画であれば、経費として計上できる場合があります。
この記事を参考にして、お気に入りの絵画を選び、節税対策や企業ブランディングの一助として役立ててみてください。
アートリエでは、絵画の購入・レンタル・オーダーなどをサポートしています。
絵画の選定から導入まで、ワンストップで対応が可能です。
税務や会計の専門的な助言は行っておりませんが、事業の目的や空間に合わせたアートの選定については、専門スタッフが丁寧にご案内いたします。
予算やブランドイメージ、設置場所に合わせて、約5,000点の作品の中から最適なアートをご提案いたします。